ARTICLES
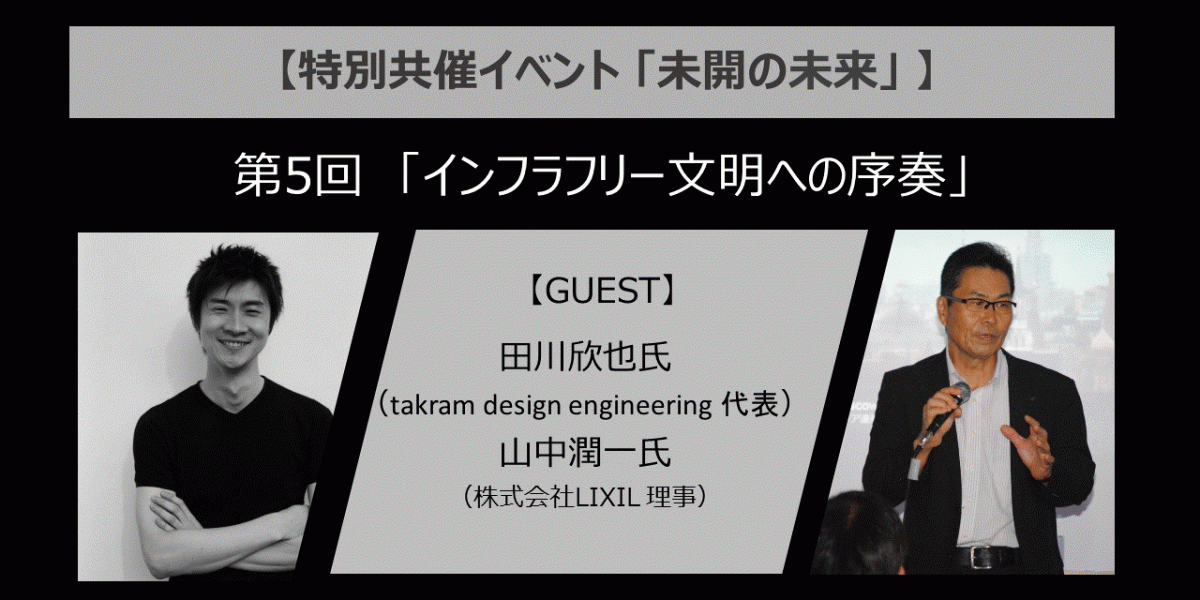
2016年7月末~10月末、東京駅から丸の内側に伸びる地下通路・行幸通りにて、世界初のデジタル地球儀「触れる地球」のプロデューサーであり、当財団の評議員でもある竹村真一氏のチームが企画する「丸の内・触れる地球ミュージアム」が開催された。「触れる地球」を5台設置した体験ミュージアム、そして全長220m にもおよぶ通路空間に「海・森・生物多様性」、「防災・減災・レジリエンス」、「未来技術」等をテーマにした演出がなされ、子ども向けから大人向けまで様々なイベントが開催された。
Next Wisdom Foundationは、8月末から毎週水曜、全9回にわたってソーシャルデザイン・ワークショップ「未開の未来」を共催。竹村氏が多彩なゲストとともに、想像力の飛距離を思い切り伸ばして未来を語り合うトークセッションだ。
第5回のゲストは、株式会社LIXILの山中潤一氏と、Takramの田川欣哉氏。現在開発が進められている災害に強いトイレと、水や電気を必要としないトイレ。そして、環境汚染が進んだ未来の地球を仮定してデザインされた人工臓器。大規模インフラの維持が困難になるであろう将来のためのテクノロジーをめぐって、自由な議論が交わされた。
【ゲスト】
竹村:「未開の未来」第2回で「車の未来 車は何に進化するのか」というテーマでホンダの開発主任の方にご登壇いただき、面白かったのが「車が命の安全保障装置、都市のエネルギー保障システムになりつつある」という話題でした。どういうことかというと、震災などで電気の供給が断たれても、家にソーラーパネルがあり車に充電できるシステムがあると、車で最低限の電力を確保できるんです。避難所に電気が来ていなくても、そんな車を集めて電力を確保することができる。つまり車が、車という名称に収まりきらないなにかに進化しつつあるというのです。
何年か前、リクシルさんが開発した「無水無電源トイレ」に出会ったとき、非常にショックを受けました。
昔の水洗トイレは一回流すたびに16Lの水を消費しましたが、すでに10年ほど前には4、3Lほどですむような超節水型トイレが開発され、さらに現在は電気や水がいらないトイレの開発が進められています。こうしたトイレは災害に強いだけでなく、上下水道の整備がないために安全で衛生的なトイレが使えない、地球人口の3分の1にあたる25億人の人々にとっても、大変なソリューションになるんです。
「未開の未来」第1回のタイトルは「20世紀文明を脱衣する」でした。20世紀型の文明は、大量の資源を使わないと安全で清潔な環境は保てないという前提でしたが、そんな前提がなくても、ある程度のクオリティ・オブ・ライフをデザインしている技術、それが次の時代の地球基準となるでしょう。これを私は「ベース・オブ・ザ・プラネット」と呼んでいます。
BOPというと、所得階層別人口ピラミッドの最底辺を意味する「ボトム・オブ・ザ・ピラミッド」というマーケティング用語がありますが、これを呼び変えたものです。そしてそのひとつが無水無電源トイレだろうと思っています。
こうした技術は、途上国だけでなく先進国でも必要とされています。最近の日本を見ているとわかりますよね。人口減少により無居住地域が増えて、遠くから水や電力、食料を運ぶ大規模なインフラを維持できなくなれば、そんなインフラに依存した20世紀型のシステム自体が維持できなくなるのです。エネルギーも地産地消を基本とするような仕組みに転換しなければ、先進国も保たない。世界中の国が高齢化問題を抱えていますから、ますます地球基準の技術ということになります。
ということで今日は新興国、先進国まで含めた新しい地球基準としての「インフラフリー」「オフグリッド」の先進例を挙げ、議論を進めます
水や電気を必要としない、新しい時代のトイレを作る
ー株式会社LIXIL 山中潤一
山中:リクシルという会社は、住まいの設備や建材などを扱う会社が合併して2011年4月にできました。
合併前の会社であるINAXでの最後の役員会途中で、大きな揺れを感じました。それが3.11。会議を中止し、すぐに災害対策本部を立ち上げました。
でも、なにもできない。悲惨な映像を見ているしかなかったんです。
避難所では、何人もの方がトイレに行けないというストレスが元で体調を崩していました。それを支援しようとトイレを送ろうとしたんですが、インフラがずたずたになっているところに普通の水洗トイレを送ったところで何にもならないんですよね。
そこで、大災害のときでも使えるトイレを作ろう、新しいトイレ文化を作ろう、と決議したのが次の年です。あれから5年、日常でも災害が起こっても使えるトイレを作るにはどうしたらいいのか真剣に考えてきました。それが「レジリエンストイレ」です。
レジリエンストイレの特徴はふたつ。従来の約6分の1の洗浄水量であること。そして、災害時は汚水を循環させ搬送水として利用できることです。
これにより、災害時でも平常時と同じように普段使いができます。バリアフリー、オストメイト対応など多機能トイレを併設することも可能です。

災害発生直後、トイレをどうしたらいいかというのは非常に大切な問題です。
たとえば避難所になるような学校や公民館、体育館といった施設のトイレを、最初から、今ご紹介した「レジリエンストイレ」にしておくと、避難所の開設と同時に使っていただけるんです。
仮設のトイレが被災地に設置されるまで早くて3日かかります。そんなに待てませんよね。それに、避難生活は長い。4月の熊本地震に遭われた方もまだ避難されています。イベントなどで仮設トイレを使われたことがあると思いますが、毎日使うには快適とは言い難い。いつも使っているトイレが災害時にも使えることが大切なんです。
このレジリエンストイレは、洗浄水量は今までの6分の1。これをさらに、ペットボトル1本分にしようにしようと開発を進めています。これだけの水すらも確保が難しい地域があるからです。そこで今、インフラを必要としないトイレの実験をケニアで行っています。
ケニアの都市部にはODA(政府開発援助)で作った水道はあります。ただ、栓をひねって水がでるのは1週間に1、2回。都市への人口集中が急速に進んだせいで、水の取り合いが起こっています。
もっとも、これは都市部の話で、上下水道などの整備が人口の増大に追いついていない地域がたくさんあります。ドブ川の水を使ったり、台所で使う水はどうにかして買っている。穴を掘って用を足しているんですが、大変ですし、飲み水と混ざってしまう恐れがあります。
そういう地域で排泄物を回収して肥料化し、農業に活用するという昔ながらの循環ができないだろうか、ということで無水トイレを作りました。
この無水トイレは大便と小便を分けます。大便にはおがくずを混ぜて水分調整します。するとすぐに発酵が始まり、汚物という感覚がなくなります。これを回収してコンポストの施設で肥料にするんです。もともとあまり化学肥料が普及していない地域なので、この肥料はすばらしい農業資材として期待できます。
この無水トイレを、ケニアの都市部や地方のインフラの行き渡っていないところに作ろうという計画を進めています。
先だってナイロビで開催されたアフリカ会議でこのシステムをご紹介したところ、各国から引き合いをいただきました。
現在は、いかにシンプルにシステムを作り上げるか、ここに注力して進めています。そして、この無水トイレが新興国から先進国に流入してくるような「リバースイノベーション」で、未来を創っていきたいと思っています。
大規模インフラを維持できなくなる時代に備える
竹村:ありがとうございました。世界初の100万都市である江戸では、栄養豊かな人間の排泄物を還元して循環させ、街をクリーンに保っていました。それを水に流して無駄にしていた近代のトイレを、革命しつつあるんですね。
山中:水洗トイレはフランスで始まりました。かつてフランスでは窓からし尿を捨てて、水で流したんです。それでセーヌ川が汚れてしまった。それで下水道システムができましたが、そこで多くのエネルギーが消費されています。
江戸は排泄物を捨てずに資源として利用していた。近郊での農業が盛んだったからできたことでしょう。今の東京でも同じような環境を復活させないと、循環はできないのではないかと思います。
竹村:この行幸通りの柱40本に貼ったポスターは全部「地球ミュージアム」の展示で、そのうちのひとつで「地下資源から地上資源へ」というトレンドについて触れています。すでにパリ協定でCO2排出量の上限が決められ、地下資源である石油は掘り出しても売れない時代が近づいています。産油国では売れるうちに売ってしまおうとばかり、減産せずに掘削を続けています。
それに対する地上資源は「都市鉱山」、つまり携帯電話や家電をリサイクルしてできる金銀銅その他レアメタルのことですが、最大の地上資源は人間や動物の排泄物かもしれないですね。
山中:そうですね。それを資源として活用すれば、処理のために使う地下資源が節約できます。
竹村:さきほど言ったたように、日本を始め先進国でも無居住地域が増え、大規模インフラを維持できなくなる時代が始まっています。そんな中、どんなビジョンをお持ちですか。
山中:トイレの次に水の消費量が多いのがお風呂です。リクシルでは、界面活性剤で泡を立てる「フォームバス」という、水量は現在の風呂の10分の1くらいの節水型の風呂を出しています。まだまだ高価ですが、もっと頑張って普及できるようにしたいと考えています。
竹村:体内に取り入れる水は、飲料と食品の水分で大体2〜3リットル。生活用水はその100倍あるわけですよね。今おっしゃった節水型の風呂やトイレ、無水トイレは、近い将来、石油に代わり水を争って世界が戦争すると言われる時代にあって、相当大きな存在です。
山中:だと思います。ただ、争いが起こってからでは遅いので、今からしっかり取り組む必要があります。
竹村:レジリエンストイレの普及はどうでしょう。
山中:今、多くの方に興味を持っていただいています。たとえば現在普及しているシャワートイレも、広く使われるまで10年もかかりました。最初はなかなか普及しませんでしたが、いいとわかると一気に広がったのです。レジリエンストイレはそれより速いスピードで普及するかもしれません。
竹村:本当に急務ですね。災害レジリエンスとしてだけでなく、インフラが維持できない無居住地域における生命維持に関わる問題になるでしょうね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
竹村:次は、体の中に水の循環装置を入れてしまおうという、究極のインフラフリーとでもいうべきとんでもないアイデアをご紹介いただきます。
考えてみれば犬はあまり水を飲みません。呼気の水分を体内でリサイクルしているからです。ラクダが砂漠で水を飲まないでいられるのも、水のリサイクルシステムが発達しているからです。こんなふうに生命全体を見れば、人間の常識は実は非常識かもしれず、未来の地球インフラはもっと飛躍ができるかもしれない。そんな大きなインスピレーションを、Takramの田川さんからいただきたいと思います。
Takramは、デザイン分野とエンジニアリング分野をつなげる「デザインエンジニアリング」という世界でも画期的な業態で、様々な企業と組んで斬新な仕事をされておられますが、今日は実用性を超えたアドバンストデザインをご紹介いただきます
水を必要としない体になるための人工臓器
ーTakram 田川欣哉

田川:21_21DESIGN SIGHTというデザインのミュージアムで、グラフィックデザイナーの佐藤卓さんと竹村先生がディレクターを務め、水をテーマにした様々な物を集めて、水について考えるという展示がありました。このとき僕らも出展させていただいたのがきっかけで、竹村先生とのおつきあいが始まりました。
普通、デザイナーとエンジニアは別々に仕事をしていますが、それが同一人格で存在しうるとしたらどんな仕事をするんだろうと仮定して仕事をしている、Takram(タクラム)はそんな会社です。
拠点は東京とロンドン。自動車メーカーから声をかけていただいて一緒にコンセプトカーを作ったり、モバイル系の会社とスマホのサービスを作るなど、いわゆるイノベーション系のプロジェクトを主に手がけています。
今日は、「ドクメンタ」で展示した作品を紹介させていただきます。
ドクメンタとは、ドイツのカッセルという小さな都市で5年に1回行われるアートのフェスティバルで、ヨーロッパだけでなく世界中の様々な人たちの作品が集まります。
2012年、僕らも声をかけていただき、建築家やファッションデザイナーなど5組が集まって未来について考えるというグループ展に参加しました。
このとき展示ディレクターから与えられたのは「100年後荒廃してしまった地球環境において人間がどうやって暮らしうるのかを、おもに衣食住3つの観点から考え直す」という設定です。建築家は住まい、服飾デザイナーは衣服、そして僕らは水を飲むということについて考えることになりました。
僕らの場合、「水だけを考えるとインフラなど社会システムのデザインになってしまうので、展示としてわかりやすいように、自然災害や戦争によって荒廃した地球環境における、人間のための究極の水筒にフォーカスを絞ってほしい」というリクエストでした。
最初は、浄水機能や湧き水探知機能の付いた水筒などを考えていたのですが、途中、さらなるリクエストを受けてゼロから考え直しました。
「100年後の未来、海面上昇や水質汚染により、人間が摂取できる水の量が、現在の5%ぐらいまで減り、今までの人類の文化や文明も断絶している。その状態でゼロから水筒を考えるとしたら、どういうものになるかをアウトプットしてほしい」
というものです。
先ほどのお話にもありましたが、成人が摂取する水の量は1日2〜3リットルと言われています。2.5リットル摂取して、2.5L外に出しているということになります。
そもそも水筒は、飲み水が手に入らない状況でも脱水状態にならないために、予備の水を携帯するためのものです。では、もし人間が水をほとんど飲まなくてもいいような生物だったとしたら、水筒を携帯するでしょうか。砂漠に生息する動物のような体を発明すれば、水筒を考える必要がなくなるのではないか? そう考えて、人間の体を擬似進化させてしまうような4種類の人工臓器と、必要最低限な水を摂取するための水を凝固させたドロップ、計5つのプロダクトのセットを作りました。
体内の水は、尿や大便、汗として排出されます。その量を、臓器の力でできるだけ抑えてみようと考えたところ、本来は水を1日2.5L摂取する必要がありますが、計算上はそれを約160ml、コップ一杯程度まで抑えられるんじゃないかというところに到達しました。
これは、頬骨の後ろのあたりに埋め込み、人間の呼気に含まれる水分を体外に出さないようにする機械です。

砂漠に住んでいるネズミの一種が持つ機構から着想を得ました。その動物は、鼻の中に生えた密集した剛毛で肺から出る湿潤な空気を結露させ、乾燥した状態で排出します。乾いた外気を吸うとその結露していた水滴が蒸発して、肺が湿潤な状態に保つのです。これを人工的に再現するため、スポンジ状に穴が空いた金属部品を抱え込んだセラミック製の部品を鼻腔に埋め込んで、体内から排出する水蒸気をカットしようと考えました。
二つ目は、発汗をコントロールする機械です。いちばん水分を使うのが発汗なので、それを止めることにチャレンジしました。
人間の発汗の大半は、大脳が発する熱を冷ますためのものです。
首の静脈・動脈を行き来する血流の温度を測ると、2度ほどの差があります。人間の血液は酸素と栄養を運ぶインフラですが、脳の発熱を血液で解消して体表で冷やすための水冷システムでもあるんですね。

この機械は、静脈と動脈の温度差を利用して微小な発電をします。この電気を首の後ろまで引いて、首輪状のラジエーターにつなげます。このラジエーターに組み込まれたファンで体外に熱を排出して体温を下げ、結果的に汗をかかなくなる、という仕組みです。
それから、膀胱に入れて尿から水分を濾し取って人間の体内に還流させる機械、大腸の付け根の結腸あたりに付けて便から水分を取り出し、体内に戻す機械で、計4個。これらの機械をつけてなお必要になる最低限の水を摂取するために。1個につき35mlの水分を固めたタブレットも考えました。
以上のような仕組みを考えました。
僕らはアーティストではなくデザインや開発をする人間なので、未来のシナリオをできるだけ緻密に考えて、その未来にいる人間にはこんな方法があるんじゃないか、と技術的に真面目に解いたつもりです。
このように、クライアントからの課題をいったん捉え直すアプローチを、僕らは「プロブレム・リフレーミング」と呼んでいます。真面目な課題を真面目に解くと、たいていはみんなが考えつくような真面目なソリューションが出てくるものですが、こんなふうに課題自体が突飛だと、真面目に解決しようとしても突飛な解が出てくるんですね。このプロジェクトを通して、そんな新しいデザインアプローチの発見にもつながりました。

そうやって生まれたこの作品はかなりシニカルです。
僕ら人間は、雨や川から採取し、浄化された水を飲み、それを排出して自然に返します。そういう意味で人間はエコシステムの一部です。
しかしこの展示が想定している自然はそれほどやさしいものではなく、生存のためには距離を置かなければいけないような厳しいものです。生きていくために、水の大部分を人間の体内でサイクルさせ、摂取・排出する水の量を減らす。つまり自然の大きなサイクルから切り離されていくプロセスを表したのがこの作品です。
これを見て違和感を感じる人、嫌悪感を持つ人たちもいますが、その反応こそが主張したいことなんです。今の僕らは、これほどグロテスクではないにしても、この展示で設定された状況に近いところで生きています。自然との結びつきからどんどん離れている人間の究極の形はここにある。でも、そうしてでも生きたいと思うだろうか、と問いかけた作品です。
人工物と人間の境界のあり方が、変わりつつある
竹村:ありがとうございました。「汚染された水環境の中で人間が安全に生きていくための水筒」というお題に対して「そもそも外から水を取らなくてもいいようにすればいいじゃないか」と捉え直す。これが問題のリフレーミングということですね。
田川さんの普段のお仕事は人間の体の外のエンジニアリングに関することが多いけれど、この作品では越境していますよね。ありていに言うとサイボーグというか。与えられた課題に対するソリューションを体の外でつくる部分もあれば、中でつくる部分もある。たとえば自動車などは、「人馬一体」じゃないですが人間の体の一部のようになろうとしていて、最近のIoTは内と外がだいぶ曖昧になっている感じがします。
田川:僕らの専門分類では、ここ10年ほど、インタラクションデザインやインターフェースデザイン、つまり、人工物と人間の間を取り持つ界面のデザインが盛り上がっています。今おっしゃったことも、この作品も、人間と自然界との境界面をいかに変質させるかが肝だと思います。
インターフェース(界面、接触面)を考えるとき、インタラクション(相互作用、相互関係)という言葉は一般的に使われますが、「インタラクション」という言葉を使うのはもうそろそろ限界じゃないか、とよく言われます。
インタラクションを訳すと「相互作用」。つまり、Aという作用に対してA’という反応があり、A’を受け取った側がBという反応を返す、というように、アクションが相互に行ったり来たりするということです。たとえばさっきおっしゃっていた「人馬一体」のような車などは、必ずインターフェース的な議論を抱えています。個人的には、人間と人工物、人間と環境の間を、アクションという単位ではなく、もう少し突っ込んで「釣り合い」という考え方で測ったほうがよいのでは、と考えています。
インタラクションというのは、CPUがまだ非常に遅くてコンピュータのアクションが人間の知覚でカウント可能な時代にコンピュータ・サイエンティストたちが発明した言葉で、今となってはやや大雑把な概念です。
たとえば今ご覧になっているプロジェクターは約30fps(※)で、iPhoneは60fpsくらいです。人間の視覚の限界は60fpsくらいで、200fpになるともう知覚外なので、その映像がデジタルなのかアナログなのか判別できないんです。
※fps=コンピュータが画像を1秒間に何回描写しているかを表す単位で、この場合は毎秒30回。動画のなめらかさを示す指標となる
人間を含む生物の知覚の中で、視覚がいちばん処理に時間がかかります。情報量が多いので、大脳で解釈するのに時間がかかるんです。一方、触覚や味覚など、視覚より原始的な知覚はもっと速い処理が可能です。視覚のように高次の、つまり生物史の後半に手に入れた感覚や器官は、人間が環境や人工物と一体化していくときの結びつきにそれほど寄与しない、とわかり始めています。
たとえば僕と竹村先生が手をつないでお互い引き合ったとき、倒れないポイントがあります。これは僕と先生の体の重心のバランスが取れている状態で、そこでは力や気持ちの釣り合いのようなところに飛躍が起こるんです。このタイプの釣り合いは、アクションの行き来というプロセスやプロトコルで記述するものではなく、「場自体が釣り合った状態である」「エネルギー的に安定な状態である」と解釈するところにシフトしていると実感します。そういうところが、今日お話ししたことに通じるのかなと思います。
竹村:もはやプロダクトデザインという段階ではありませんね。プロダクトを体の外側のものとしてデザインしている限り、人間と物や環境の間をつなぐようなデザインはできない、と。
田川:そうです。面白いことに、場が釣り合った瞬間、個と個の間も釣り合うので、境界面は消えるんです。仮に僕と先生が手をつないでいるとしたら、常識的には僕の皮膚と先生の皮膚の間には境界があると考えますが、力学上は、僕一人の腕の関節が釣り合っている状態と違わないんです。
今、それと同じようなことが、人間の知能と機械の知能との間に起こり始めていると思います。だから、その部分をデザインしたり、エンジニアリング的に解釈していくための新しい単位のようなものが必要になっています。
竹村:後から獲得した感覚のほうが遅くて無駄が多い、ということは、ある意味よくあることだと思います。
たとえば人間の立体視は、5000万年前くらいの初期霊長類の頃、樹上生活の中で枝と枝の間の距離を図るために獲得した感覚だと考えられます。つまり特定の環境下では必要だけど、情報処理の速度だけならトンボみたいな複眼のほうが速いということもあるでしょう。
これからの自動車が実装する視覚的な機能が鷹の目なのかトンボの目なのか、生物界にはそのヒントたくさんあるわけですよね。そう考えると、人間だけを基準に考えると選択肢が狭まるかもしれないですね。
田川:はい。人間という存在の輪郭線をどこで設定するかによっても、その幅は変わるでしょう。特に機械や人工知能がさらに強化された時には、その定義がすごく大事になってくると思います。
竹村:この方向でもう少し続けたいところですが、また改めて企画させていただくとして、山中さんに再び登壇いただきましょう。
20世紀の制約を超えて、文明が飛躍する準備はできている
竹村:今のテーマとのつながりからお話しますと、実はリクシルさんはもうひとつ、「汚れないトイレ」を開発されています。陶器の表面がナノ構造で汚れがつかないというもので、そのヒントが生物だとうかがっています。
山中:カタツムリの殻の構造を生かしたものです。バイオミミクリー(生物模倣技術)の一環です。
田川 カタツムリの殻って油性マジックで書いてもこびりつかないんですよね。適度な湿度になっているとこびりつかないとか。
山中:そういうことです。
竹村:バイオミミクリーによってイノベーションが進んでいるという実感はお持ちですか。
山中:多くの人が生物にヒントを求めていると感じます。
ところで今日のお話で非常に興味深かったのが、人間の体の中に機械を組み込んだところです。私どもは住生活や家を中心に考えていますので、人の体に押し込めなくても、同じ機能を家の中に作ることはできるようになるんじゃないか、と思いました。
竹村:そこは分ける時代ではないのかもしれません。
たとえば、体の中で呼気の水分を循環させるシステムと、体の外に排出した小便を近隣の農業に利用するなどして循環させる仕組み。体の外か内かという区別があるけれど、どちらも、人間による20世紀型の都市のシステムが膨大な無駄を生み出す大変なバッドデザインだったということを明らかにしています。
山中:そうですね。人口密度が高い時代にはそういう大規模インフラが成り立ち、そこに大きな意味の循環が生まれていましたが、人口減少が進むと、もっと小さな循環の単位が必要になります。その究極が体内で循環させてしまう機械、ということですね。今はまだ、家単位で実現する段階でしょうか。
竹村:ヒートテックのような衣類も、水分を介した熱循環を利用しています。そんなことも考えると、住む服、着る家、というように、衣食住の境界も曖昧になっていくように感じます。
田川:未来予測的な仕事の中で、必ず出てくるのが「コンパクトシティ」の構想です。国土の端から端までインフラを保持することができないので、人をできるだけ都市部に集めて効率的にインフラを提供していきましょう、その圏外はもうメンテナンスしないことにしましょう、という議論です。
もちろんこの方向で進めていく必要もあると思いますが、その流れに乗り切れない人たちの暮らしを技術や社会がどう保障するのかも大きな問題です。
今までのインフラの規模って、都市設計上、電力や水などすべて100〜200km圏くらいですよね。それを数100mとか1km圏内でそれぞれに独立した小さなシステムを築くことが必要になるでしょう。
山中:近年は震災がそういう孤立状態を作りました。それを解決する必要性は感じます。
竹村:リクシルさんの仕事でもうひとつ画期的だと思うのが、HOUSE VISIONで発表された水周りです。
今のトイレや台所は家の中で分散しているため、たくさんの配管が必要で、非効率でもあります。それをワンユニットにしたものです。これなら一本配管があれば事足りるし、これを持って引っ越すのも簡単。これもインフラフリーのひとつの方向性ですね。
山中:そうです。給排水と給排気のシステムをまとめたもので、オアシスと呼んでいます。
竹村:東京の水需要は大体年間20億トン前後、それに対して東京に降る雨の量は25億トンだそうです。ですから遠くにあるダムから水を引いてこなくても、雨だけでも十分まかなえるはず。つまり雨水利用のシステムと、ひとまとめになった水回りシステム、そして水を使わず排泄物も循環させていくトイレが組み合わさると、生体に近いシステムになっていくと思うんです。
山中:水を浄化して使い、汚れたら処理して戻す。これは20年前に技術としてできあがっています。今後は、それをエネルギーフリーにすることが課題です。太陽の光をうまく集めて蓄熱すれば、水を蒸発させて浄化することもできるでしょう。急がないといけませんね。
竹村:地球上では、汚れた水を太陽が温めて蒸発させることで浄化し、それが循環しています。そんな地球規模のシステムを、都市のスケール、あるいは我々の等身大のスケールでやっていくということですね。古いしがらみや古いインフラを捨てられない、そういう問題はありますが、20世紀型の文明の制約を脱ぎ捨てる準備はできているんですね。
途上国で、電話線が引かれていなかったからこそ固定電話の段階を踏まずに携帯電話が一気に普及したのと同じように、上下水道などのインフラがないからこそリープフロッグできるかもしれない。そんな可能性はお感じにりますか。
山中:今ケニアで実験中のトイレに、その可能性は十分にあると思います。
竹村:田川さんはどうお考えですか。
田川:20世紀型の上下水道や送電線の仕組みは、爆発的なスピードで人口が増えている状況と、それをサポートする当時のテクノロジーに見合う形だったんだと思います。
今の新興国は先進国に蓄積されているテクノロジーを利用できるので、道具やシステムの進化の条件が違うんですよね。携帯電話もそういうことで、仮に僕らが20世紀の後半にタイムスリップして、その時点で携帯電話があれば、だれも電話線なんて引きませんよね。送電線さえ引かなかったかもしれない。
先進国も人口縮退に入っていくので、20世紀とは条件が全然違います。日本は真っ先にその状態に突入するので、ケニアなどで起こっていることとは違うけれど、今までと異なるパラダイムが合理的になるという点は先進国も新興国も同じような状況だと思います。
ただし、20世紀の常識とはかなり掛け離れるので、「なぜそれが合理的なのか」「条件設定がどうシフトしているか」というコンセンサスを作り、今日のような議論を持ちながらイメージを固めないといけないだろうと思います。
山中:トリガーが必要ですよね、きっと。
田川:地震はそのひとつなんでしょうね。過激な条件が強制的に設定されたというか。
竹村:20世紀に僕らが文明と呼んでいたものは、実は幼年期の未熟なものだったんですね。
せっかく地下資源を掘ってタンカー100積分の石油を運んできても、火力発電所で電気にして、発電、送電などを経て9割以上のエネルギーが失われます。
自動車も、古いタイプならエネルギーの9割方がエンジンの排熱やタイヤの摩擦で失われ、残りの1割近くを重い車体を運ぶために使い、僕らの移動のために使われているのはたった1%。つまりタンカー100積分のうち99隻分を捨てるようなものを、文明と呼んできたんです。
先ほどお話に出たバイオミミクリーの例をひとつ。世界一のスティールメーカーがものすごい強度のワイヤーを製造するためには、大量のエネルギーを使って高温高圧をかけることが必要である一方、それよりはるかに強くて柔らかいファイバーを、クモのような生物が常温常圧でやってのけています。
ほかの生物のノウハウを獲得して、人間が人間という制約を超えていけるかもしれないとなると、僕らの文明はこれから本番だという感じがします。それが「未開の未来」、つまり未来はまだ全然開かれていない、ということなんです。
ここで、タクラムからいらしていただいたもうお一方をご紹介します。渡邉さん、ひとことお願いします。
一見突飛なアイデアこそ、未来への牽引役になりうる
渡邉:突然すみません。Takramの渡邉と申します。
災害後や後進国でまさに必要とされていて、今後も確実に世の中に寄与するであろうリクシルさんのものづくりについてのお話と、すぐ実用化できるわけではない、まだ存在しない100年後のためのタクラムのものづくりについての話、絶妙のバランスの議論だと感じました。

5年前に人工臓器を作ってドクメンタで展示したとき印象に残ったことがあります。大抵の人はこれを見てギョッとして、体を改造してまで水循環を取り入れたいと思わない、と言いますが、ある女性ジャーナリストが「この首輪はいつ実用化されますか」と声をかけてきたんです。我々のほうがびっくりして理由を聞いたら、実は彼女には子供がいて、5歳くらいの男の子らしいんですが、汗がかけない病気で、体温があがると熱が発散できずに倒れてしまうんだそうです。運動ができず、友達と遊ぶことができないから、こういった首輪が開発されたらすぐにでも着けてあげたい、と。
誰かにとっての非常識は、誰かにとって必要なものになりうる。100年後を想定した突飛なデザインでも、今の時代に役立つかもしれないということにショックを受けた瞬間でした。
当然、今必要なものはつくるし、未来に先駆けてつくることもやっていきますが、どこにたどりつくかもわからないデザインも、非常に大きなインパクトを世の中にもたらすんだな、と。
たとえばクローン羊のドリーが生まれたとき、それによってどんな臓器移植が可能になるかという議論より、そもそも生命の創造に人間が踏み込んでいいのかという議論のほうが盛り上がりました。しかしそこに拘泥していては技術や世の中は進まないかもしれなくて、デザインやイノベーションをきっかけに常識を刺激したり倫理自体を新陳代謝していく、その循環が大事なんだと思いました。
今日の議論は、今必要なインフラをつくり続けるという非常に大事な部分と、考え方や常識自体を牽引していく部分、両方がある貴重なものだと感じました。
竹村:ドリーやiPS細胞などで人間が生命の創造に踏み込んだとはいっても、やっていることは「腎臓になってね」とか「脳細胞になってね」と表面的にナビゲートする程度で、それを司るのはやはり細胞そのものです。そもそも、今はまだようやく生命のすごさや面白さがわかってきた段階で、生命を操作するレベルには到底到達していないとも言える。その意味でも未開の未来なんですね。
数日前、隈研吾さんをこちらにお呼びして、国立競技場についていろいろうかがった中で最も面白かったのは、木造建築の新陳代謝についてです。
法隆寺がなぜ1400年建っているかというと、部材をどんどん入れ替えられるからなんです。石造りのパルテノンがなにも入れ替えずに1000年2000年建っているのと全然違う。我々の体をつくっている細胞が常に新陳代謝して、自分を壊しつつ新しくし続け、同時に昨日のままでいるように、法隆寺も、1400年前の部材はほとんどないけれど、新しくなりながら1400年、法隆寺のままでいるんです。
これからは自己修復できるようなインフラもありうるでしょうし、部材単位で入れ替えながら200年住宅、300年住宅というのも可能になるのでは。そういう生命系に近い循環、自己修復をするシステムという意味でのデザイン論や住宅論を、今日の最後に聞かせていただけますでしょうか。
山中:隈さんの設計した国立競技場は、700mm長さで105mm角の集成材を使ってつくる、レゴで組み立てたような構造なんですよね。その材は人が手で運べるし、どんな木を使ってもどの製材所でも製造できる。特別なものではないんです。構造の芯になる部分があって、それをしっかり守るために他の部分は代替可能。そういう思想がある設計なんですよね。
特定の会社やメーカーでしか作れなかったり、交換不可能、そういう思想ではダメなんですね。
私どもで作っているトイレについて言うと、100年保つセラミックスは製造できます。ただしシャワートイレのコンデンサーが10年保たないので、それだけパーツとして分けるという考え方をしています。
田川:技術の大幅な置き換えは、非線形的に起こることが多いんです。つまり、自己修復のように自己保存性の強いものではなく、別種の「はぐれもの」がいきなり登場して、旧来の種を打ち壊してしまう形で技術進化が起こっていく傾向があるんです。
技術や素材などの進化がある程度落ち着いて、成熟したものを再構成していくときには、先生がおっしゃったような自己循環型の設計思想が適していて、まだなにが最適かわからず、いろいろなチャレンジが起こる進化の途上では、発散的で多様で、ある意味乱暴で破壊型の進化のほうが適しているかもしれません。
20世紀型の技術の大半が、この乱暴な段階なのではないでしょうか。そのやんちゃで若い時期を抜けて、成熟して落ち着いていくフェーズに移行すべき技術が、今もまだ自然に対して乱暴な状態で居座り続けているのかもしれない。今見えているもののどれが前半にあたってどれが後半にあたるのかを考えてみたい、と、先生の問いかけから考えました。
竹村:この議論を続けたいですね。ただ時間の都合があるので、次のラウンドへのキューを出しましょう。
遺伝子とは40億年前からあるデジタルシステムです。このデジタルシステムは、99.9%のミスを排除する究極のコピーシステムであると同時に、0.01%でも誤りを許容すると大幅な革新もできる、つまり保守と革新両面に向いたシステムです。だから、60億対ある遺伝暗号の1文字が変わっただけで体質かがらっと変わったりするわけですね。そしてこのシステムをベースにして、豊かなアナログの世界が形成されています。21世紀前半、ここに人工のシステムがどうアクセスできるか問われていて、iPS細胞すらまだその裾野にたどり着いたくらいだと思うんです。
もうひとつ、生態系のシステムでは、たとえば、樹木に寄ってくる動物やバクテリアは100年1000年も経てばどんどん世代交代しますが、樹木そのものは、細胞は入れ替わっても整合性のある木質部分を維持できるOSを持っています。そしてこの樹木がある意味生態系の軸になっています。
未開の未来に対して人間を解放していくためのヒントとしての生命系を、ようやくこれから発見していく段階に入ったところなんですね。まだ足がかりの議論でしたが、多くの宿題をいただいたように思います。ありがとうございました。

