ARTICLES

人間らしさを追求しながら生きたとしても、その先に必ず待っているのは「死」。死を考えることは、生きることを考えることでもあります。死生観は、時代の流れによって変化していくのでしょうか? そして、医療や宗教との関係性は? 来たるべきその時に備えて死を前向きに捉えるために、東京大学死生学・応用倫理センターの池澤優先生にお話を伺いました。
〈プロフィール〉
池澤 優さん
東京大学大学院人文社会系研究科(文学部)/死生学・応用倫理センター長、宗教学宗教史学研究室教授
専門とする研究分野は中国古代宗教、祖先崇拝、死生学、生命倫理、環境倫理。もともと出土資料文献を用いて古代中国の死者儀礼や祖先崇拝を研究することを専門としていたが、2002年から東京大学文学部の死生学プロジェクトならびに応用倫理教育プログラムに関与し、死生学と応用倫理の分野も専門とするようになる。2011年に死生学・応用倫理センターの創設と共に、センター長に就任
生と死の哲学
Next Wisdom Foundation事務局(以下、NWF):まずは死生学について、わかりやすくご説明いただけますか。
池澤 優(以下、池澤):死生学は、英語では“Death and Life studies”、“Thanatology”などいろいろな名前がありますが、学問として確立したのは1960年代です。専門家の間では、1959年にヘルマン・フェイフェル(Herman Feifel)という心理学者が死に関する論文集を出したことに始まるというのが定説になっています。それで50年代の終わりから70年代の初めにかけて、主に心理学者の中で「死ぬこと」と「死にゆくこと」(Death and Dying) をテーマにする学術領域が出てくるわけです。
なぜそういう分野が台頭してきたかというと、一つには死そのものは昔から人々の関心の的だったからということがあります。当たり前ですが、人間にとってすごく大事なことですよね。
しかし、それ以上に、当時、欧米では公共空間から“死の現象が消滅する”事態があったという要因がありました。ジェフリー・ゴーラーというイギリスの研究者はそれを「死のポルノグラフィー」と呼んでいます。たとえば、愛する人が死ねば悲観に暮れるのが当然ですが、その悲観を公共空間で見せるのはおかしい、病気であるという風潮です。1960年代くらいから、そのような風潮を反省する“Death awareness movement”という運動が、私は「死の認知運動」と訳していますが、起きてきます。その中では、現代人は死から目を背けて生きている、だからいざ自分が死に直面すると見苦しい死に方をすることになる。だから、死を直視して、前向きに乗り越えて生きていこうという主張がされます。そのような運動の一環として、死生学という学問が成立したと言えます。
但し、以来、60年ほど経っているわけで、死生学にも当然大きな変化がありました。当初は、いま言ったような事情で「死を乗り越える」「死を受容する」という点に強調点が置かれたのですが、「それはおかしいんじゃないか」という意見が1990年代に出てきて、今はそういう考え方はしなくなっています。
NWF:では、日本ではどのように死生学が確立していったのでしょうか。
池澤:日本に死生学が持ち込まれたのは、1975年。上智大学のアルフォンス・デーケン教授が最初に死の哲学について講義したことがきっかけです。80年代の初頭には、彼のイニシアティブの下で『生と死を考える会』が成立し、現在も活動しています。デーケンさんはシンポジウムや研究集会に多くの研究者を引っ張り出して、たくさん論文集を出しながら、日本で死生学を成立させていきました。
ただその後、大きな動きがあります。デーケンさんは神父です。つまり、初期の段階で彼の周りに集まった死生学関連の研究者は、キリスト教徒が多かったわけです。結果的に、彼らの死生学の運動には宗教がかなり深く入り込むことになりました。「信仰を持つことで、死を受容する」ということです。だから、デーケンさんの死生学の柱のひとつは、死後の存続でして、死後の霊魂があることを信じて前向きに生きることが、希望になるということでした。
それが日本人の感覚にちょっと合わないところがあって……合うところもあると思うのですが。自分が死んだらすぐ無になると思っていても、愛する人が死んで直ちに消滅するというのは、感覚として受け入れにくいのではないでしょうか。とはいえ「死後も霊魂があるから、希望を持って明るく死んでいこう」というのは、やはり日本人の感覚には合わないですよね。そういうわけで、80年代の後半にそれらとは違う考え方が出てきます。
その中のひとつが、清水哲郎先生が始めた臨床死生学会です。これは主に医療関係者を対象とした学会で、デーケンさんの死生学が一般の人々の「生き方」という問題をテーマにしているのに対して、臨床現場で意思決定をする時に死生学の知を届ける、というのが大きな特徴です。
そのような動きがあった後に、我々の死生学のプロジェクトが始まります。本プロジェクトの初代リーダーが島薗進という私の同僚で、私の死生学の構想もだいたい彼から受け継いだものです。
島薗さんは「我々の死生学は3つの柱から成る」と言いました。一番目は、現在進行形で起こっている現場、特に臨床現場で起こっていることから学ぶということ。二番目は、過去の人類の叡智。思想と歴史に照らして、現在起こっていることの意味を考えることです。このふたつの関係は、現在から学んだことを過去の知に照らして理解し、そこから得たものを現在に活かしていくという相互関係がある。でもそれだけではダメで「では我々はどう生きていかなければならないのか」という未来における構想に繋げてなければならない。これが三番目です。生と死に関する哲学ですね。

病院で死ぬことが主流になっている
NWF:過去には戦争があったし、医療も今ほど発達していないし、本当に身近に死が溢れていたと思うのですが、それがどんどん変わっていますよね。死というものが見えなくなってきてもいる。
池澤:20世紀後半から病院で死ぬことが主流になっていて、現在でもその状況は続いています。ただ当時からそれを明らかに見える形にしていかなければいけない、という運動も生まれています。それが死生学でもあるし、教育の領域でいえば命の教育やその実践、ポピュラーカルチャーでは『おくりびと』のような形で死の文化を表現する現象も出てきています。我々のシンポジウムでもテーマにしましたが、現在は超高齢化が大きい問題ですね。
NWF:どんどん死ねなくなっていますよね。
池澤:そういうことですよね。もしくは、ある一定の死に方というのが一般化している。
NWF:8〜9割の人が、病院で死んでいるということですか。
池澤:もちろんそうです。
NWF:日本の死生学は臨床現場と繋がっていたり、クリスチャンの考えとは違っていたりするということですが、世界から見た日本は特異なのでしょうか?
池澤:宗教に関して言えば、実は欧米の死生学の中でもかなり考え方に違いがあります。ここは難しいのですが、どこまでが死生学の領域かというと、専門家から見てもとてもわかりづらいですね。例えば、死生学に関係する領域として、アメリカのような場合ですと、病院にチャプレン(宗教者)がおり、患者の宗教的なニーズに対応しています。その場合は学問ではなく、宗教的な実践と言えることになります。一方で、死生学の中核部分に、それを学問として研究しようとしている人がいることも確かです。ただ、死生学の専門家の中でも宗教をプラスに評価する人もいるので、一概に言うことはできません。
NWF:つまり今までは、宗教の役割が大きかったということですよね。
池澤:そうですね。あまり一般化するのは良くないのですが、オーストリアにヴィクトール・フランクルという心理学者がいました。彼がロゴテラピーという精神療法を始めるのですが、それが死生学の初期形態になりました。彼が主張するのは、宗教をポジティブに評価するということ。つまり、一定の価値観、宗教的な価値観を選択することで、自分の生死に意味付けを行うということです。しかし一方で、アーネスト・ベッカーというカナダの心理学者は「現存の宗教はすでにリアリティがない」と言いました。欧米において、死生学にはそういう両極の立場があることも事実です。
病院から自宅へ運ぶ救急車
NWF:死生学は、社会や文化的な背景によってそれぞれに発展しているのですね。
池澤:死生学は現実問題と向き合っていく学問なので、国によってどのような死生学になっていくかは異なるんです。欧米の場合、少なくとも最初からメインの問題は「死」と「死にゆくこと」(Death and Dying)だった。日本の場合は先ほどお話しした我々のプロジェクトがそうであったように、そこに「どう生きるのか?」という問題を入れるべきだという話になります。
東アジアに関して言うと、死生学が一番進んでいるのは台湾です。もともと台湾出身で、アメリカの大学で死の準備教育(Death Education)を担当していた傅偉勲(ふ いくん)という人が台湾に死生学を持ち込んだという経緯があります。彼は宗教学者で、意識的に宗教信仰を選択することで生きることの意義を定めることを死生学の柱にしました。台湾の死生学は現在もある程度、宗教色が強いと思います。また台湾の大学に死生学の組織が作られるのが1997年だったんですが、同時期に台湾で国民健康保険の改革があり、それが末期医療と死のあり方を変えてしまったという事情がありました。それまでは、最期に病院で死ぬ人のパーセンテージがとても低かった。病院死が自宅死を上回るのが、確か2012年かな。
NWF:そんなに最近なんですか?
池澤:病院に行かないというわけではないんです。入院はしているんですが、臨終状態になると退院するという慣行があります。「家で死にたい」ということですね。
NWF:日本でも家での看取りを希望する人が増えているようですね。
池澤:ただ、家で介護して最期そのまま死ぬという話ではなく、あと数時間で死ぬという状態で退院するんです。いろいろな管が入っていますから、それらを抜管して、救急車に乗せて自宅に帰るんですね。
NWF:救急車の使い方が逆ですね。
池澤:そう。それで最期は家でも、一応、死に方がちゃんとありまして。家の中心の部屋に置かれた祖先の位牌の前で死ぬ、という一種の作法があったわけです。ところが医療制度の改革によって、一気に医療水準が高度化し、簡単に退院できなくなった。それで、病院で死なざるを得なくなったんですね。
するとどうなるかというと、今まで家で行っていた“いい死に方”ができなくなったので「病院でそれをやりたい」という話になりました。つまり、病室で宗教儀礼をやりたいと。これは助念(じょねん)というのですが、臨終の時から周りでたくさんの人が念仏を唱え始めて、死後10時間ほど続けるということを病院でやるという流れになっています。
そのような流れで、台湾での死生学の定着というのは、ある宗教学者が持ち込んだだけでなく、医療の変化に乗って死生学の制度化が行われたという感じですね。
また韓国の翰林(ハンリム)大学というところにも、生死学研究所というものがあります。韓国で起きている全体的な動きは把握できていないのですが、翰林大学は地方の大学で、政府からお金をもらって生死学研究所を作りました。それが韓国で注目を集めた理由は、自殺問題にあります。韓国は、日本と比べ物にならないほど自殺率が高いんです。日本の場合は中高年の自殺が問題になっていますが、韓国の場合は若年層の自殺が多いですから。

自分が死んだら「無」になるのか?
NWF:いま日本で死生学を学ぶ大きな意義とはなんでしょうか。
池澤:論文にも書いたのですが、日本で制度化された死生学というのは、実はそれほどあるわけではありません。実践例のひとつが、先ほど申し上げた島薗さんがリーダーを務める上智大学で、2016年に大学院の実践宗教学研究科の中に死生学専攻を作り、実践者を養成しています。もうひとつが高野山大学。真言宗の大学で、死生学のコースが存在しています。さらに東洋英和女学院大学にも、死生学研究所があります。最後に、私たちのいる東京大学大学院ですね。
NWF:でも「終活」という言葉があるように、今後注目が高まっていきそうですね。
池澤:死生学に対する一定程度のニーズは間違いなくあると思います。授業でも死生学概論を行っていて、履修している学生数も増えています。
NWF:これからさらに発展していく可能性を秘めているということですね。では日本の死の現場、あるいは死生学の課題やテーマはなんでしょうか?
池澤:間違いなく高齢化でしょう。
NWF:伺ったお話だと、ほとんどの人が病院で亡くなります。病院で迎える死については、どういった議論があるのでしょうか。
池澤:その段階で問題になるのは、終末期の患者・家族に対するケアと、患者が亡くなった後の家族に対するグリーフケアですね。具体的には、人生の最終段階における意思決定。私たちのセンターでは寄付講座(上廣死生学・応用倫理講座)で、臨床現場の医療従事者向けに「どういう診療を行ったらいいか」「その意思決定はどのような過程でなされるべきか」という問題を扱っています。現実問題としては、これが一番大きいわけです。ただセンターとしては、もちろん臨床の問題は大事ですが、その問題だけでなく死生観全体を扱うことを目指しています。
NWF:武士の時代の死生観や、世界大戦の時の特攻を生み出してしまった死生観、そして現代。だいぶ変わってきているとは思うのですが、今後も変わる可能性はありますか?
池澤:それはものすごい勢いで、今も変わりつつあると思います。今の、というより、近代の、と言ったほうがいいでしょうか。1962年に亡くなった宗教学者に、岸本英夫という人がいました。私の先生の先生です。宗教学者ですので、当然、死のことは普段から考えている人でした。彼はアメリカに招聘されて行った時に皮膚ガンになりまして、当時日本では行われていなかったガン告知をされました。それでアメリカで手術を受け、一応成功して帰国するのですが、日本で再発するんですね。そこから10年間、再発したら手術……という生活を送り、亡くなりました。
彼は自分自身が死に直面して、どういう気持ちであるか、かなりたくさんの文章を書いていました。亡くなった後にそれらをまとめて『死を見つめる心 ガンとたたかった十年間』という名前で本を出し、それが相当多くの人に読まれたと聞いています。彼はガンになった当初、パニックになるんです。ところが、自分が受けてきた教育というものがあるので、死後の魂についてどうしても信じることができない。つまり、自分が死んだら無になるということで、それは身の毛がよだつほど恐ろしいと書いています。
ところが、日本女子大学の創設者で、やはりガンで引退した成瀬仁蔵先生の最終講義の講演録を読んで、考え方が変わるんですね。岸本さんはそれまでは怖さを忘れようとしてがむしゃらに働いていたのですが、その講演録を読んで「自分が死んでも世界は残る」ということに気づくんです。それまではおそらく自分が死ぬと、知覚する主体がなくなるため、世界がなくなるような感覚に陥っていたのでしょう。そして「死は別れである」と考えるようになります。死に直面しているといってもまだ生きている。生きている人間にできることは、生きることだけなんです。だから最期までいい生き方をして、さよならとみんなに告げ、その時が来たら「大いなる宇宙に戻っていく」というような表現をされていました。
これを私の視点から見ると、死というものは、現世からの退場ではないかと思います。自分はその場からいなくなりますが、残っている人に委ねれば、やり残したことを継いでくれる。その場合でも、当たり前ですが未練は残るんです。でも逆説的ながら、未練があるから死を受け入れられる。そういう風に、捉えているのではないでしょうか。
死は人間に定められた運命ですから、悲しくて口惜しいけれども、他人と同様、自分もその大いなる摂理の中にいる。日本の近代の死生観は、こういう考え方がかなり強いかなと思います
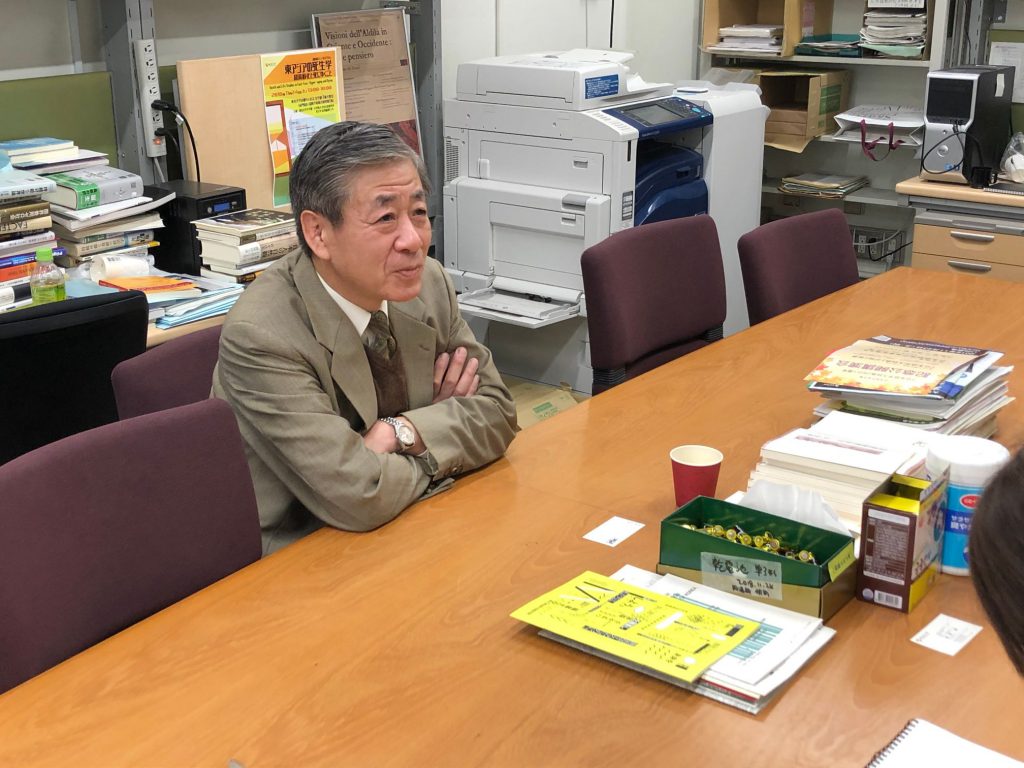
安楽死による「死ぬ権利」
NWF:現世からの退場というのは「次のゲームにもまた出られる」という、輪廻転生の概念ですか?
池澤:それはないですね。アンケートを取ると輪廻転生や死後の世界を信じている人が相当数いるのですが、専門家に関して言うと少ないですね。それが日本の特徴なのだと思います。
NWF:今もある意味そうやって、自分なりに考えて死を受け入れることはできるけれども、宗教が強かった時代は、宗教の世界で死を受け入れていたわけですよね。
池澤:それはどうでしょうか。既に退職されましたが、北海道大学に宇都宮輝夫さんという教授がいらっしゃいます。彼はかなり早い段階から死生学の研究を行っているのですが、おおむね「宗教の教義というのは生に対する意味づけを後から論理的に表現したものであり、付け焼き刃的にそれを受容しても、そんなものが人間の価値観を変えるわけがない」といったニュアンスのことを言っておられます。逆に言えば、宗教を本当の意味で生活体験の中で納得して捉えた時、初めて自分自身の死生観になり得るということでしょう。
広島の被爆者の調査を行っているロバート・J・リフトンというアメリカの心理学者は、宗教によって生と死を受け入れている人はいると言います。ただそれは決して多くはない。リフトンが挙げている例は、原爆で6人の子どものうち5人を亡くした母親で、「子どもを救えなかった」という罪の意識があり、牧師さんに「あなたの罪はすべてイエス様が背負ってくれます」と言われて改宗した、というような人なんです。そういう意味で宗教は確かに人を救う可能性があるけれども、一方で宗教の教えを自分の中で消化しきれていない人は死の恐怖が勝ってしまうので、「宗教があるから死を受容できる」とは簡単に言いきれません。
NWF:宗教は、サポートしてくれるイメージですね。最終的には、自分の中で消化するしかない。そういう意味で、先日NHKのドキュメンタリーで見たのですが、スイスでは安楽死が合法とされていて、自分で死を選べると知りとても驚きました。そういった、安楽死制度や権利について、死生学の立場からどう思われますか?
池澤:大きい問題、かつ微妙な問題ですね……。(しばし考える)
それは生命倫理、応用倫理の問題にもなりますよね。応用倫理という問題でいうと、私の基本的な考え方としてはこう言えるかな。
生命倫理だけでなく、例えば環境倫理でもそうなのですが、欧米ではまず原則を明らかにします。生命倫理の場合、自律(autonomy)が最大の原則。本人が自主的に選択するのであれば、その原則の延長線上に安楽死、もしくは医師幇助による自殺を認めるべきで、法制化もするべきであるという議論もあります。逆に個人の生命の尊厳原則に照らして、それは神の領域を犯すことであり、認めることはできないという考え方もあります。
問題は、原則と原則が対立した時にどう調整するか。原則から結論を導くのは哲学的には筋が通るのだけど、その結論は社会的にはどこかおかしいという状況もあるのではないか、というのが私の課題で、例えば告知という問題で捉えた場合、生命倫理の中で告知が肯定されるのは、告知によって自己決定できるという理由によります。告知されなければ自己決定ができませんから。しかし、自己決定という原則が告知を肯定する唯一の根拠であるのか、言い換えれば、自己決定という原則を重視しない文化は告知を否定することになるのかどうか、根本的に疑問があると思います。告知しなければ、まだ時間があると思っていて、大事な機会を逸してしまうことになりかねません。実際に東アジアでは「告知しないと死に対する準備ができないから」という実際的な理由で告知が行われていました。
ですから一般化してお話しするのは難しいのですが、安楽死ならびに尊厳死の問題に関して、原則から一般的対応を導き出すという考え方はあまり生産的ではなく、もっと個別の状況について賢明な選択をするべきというのが私の基本的な考え方です。
それでいうと、まだ尊い生き方ができるのに、本人が死ぬと決定したからといって「ああそうですか、死なせてあげましょう」というのはおかしいですよね。同時に医療的な施術は、何らかの効果がある可能性がありますが、副作用もあって、延命しようとして苦しい状態に陥ることもある。しかもそんなに寿命を伸ばせるかわからない場合、その技術を用いることが果たして賢明なのかどうか。だからケースにより、どのような選択が一番賢いのかというふうに物事を考えていくべきだと思います。

生命は、自分が退場しても続いていく
NWF:そのドキュメンタリーでは、スイスの場合は「積極的安楽死」を選択でき、日本では「消極的安楽死」、つまり延命措置をしない安楽死がとられていて、ひとくちに安楽死といっても二種類あるということでした。
池澤:実際は、医療行為の“差し控え”に反対する医療従事者はほとんどいないと思います。患者が「その行為は不要です」と言えば、だいたい認められます。しかし、医療行為の“中止”はおそらく認められません。我々にしてみればどちらも同じステータスのように思えるのですが、医療者にしてみれば、中止は「行う」ということなんですね。「入っていた機械のスイッチを切る」というような行為は、命を止めることにつながりますから。
NWF:これから人生100年時代と言われますが、寿命が延びることで人の死はどう変わっていくと思われますか?
池澤:さっき申し上げたように、終末期の意思決定が大事、という風にしばらくの間はなるでしょうね。
NWF:寿命が延びるというのは、ある程度先延ばしにしているだけかもしれないですよね。
池澤:85歳を過ぎると、生きているだけで非常に辛い状態になりますよね。その状態で生きていくとなると「どうやって生きるか?」という問題の方が、死よりも事実上大きいでしょう。
NWF:先ほどお話しいただいた「未練があるから死を受け入れる」ということについて、矛盾しているようにも聞こえるのですが、もう一度パラフレーズするとどういうことでしょうか?
池澤:詩人の高見順はこういう内容の詩を書いています。自分は末期の病気で入院するために駅で電車に乗ろうとする。すると若者たちがたくさん電車を降りて、楽しそうに話しながら歩いていく。自分はこれから死を迎えるために入院しようとしている。その隣を若者たちが通り過ぎていく……。高見は「君たちに会えたことはうれしい」「青春はいつも健在なのだ」と述べ、「さようなら 私の青春よ」と詩を結びます。
自分は退場していくわけですが、生命というのは自分が退場しても続いていく。それが希望ということだと思うんです。もちろん自分の退場は未練なんだけど、同時にそばに生命が残ることは希望である、ということですね。自分が退場しなければならないということは託す人を必要とする、託すものがあるということであり、その裏には、生命は続くという感覚がある。続いていく生命に希望を託すことで、自分の死を受け入れることが可能になる、そういうことだと思います。


